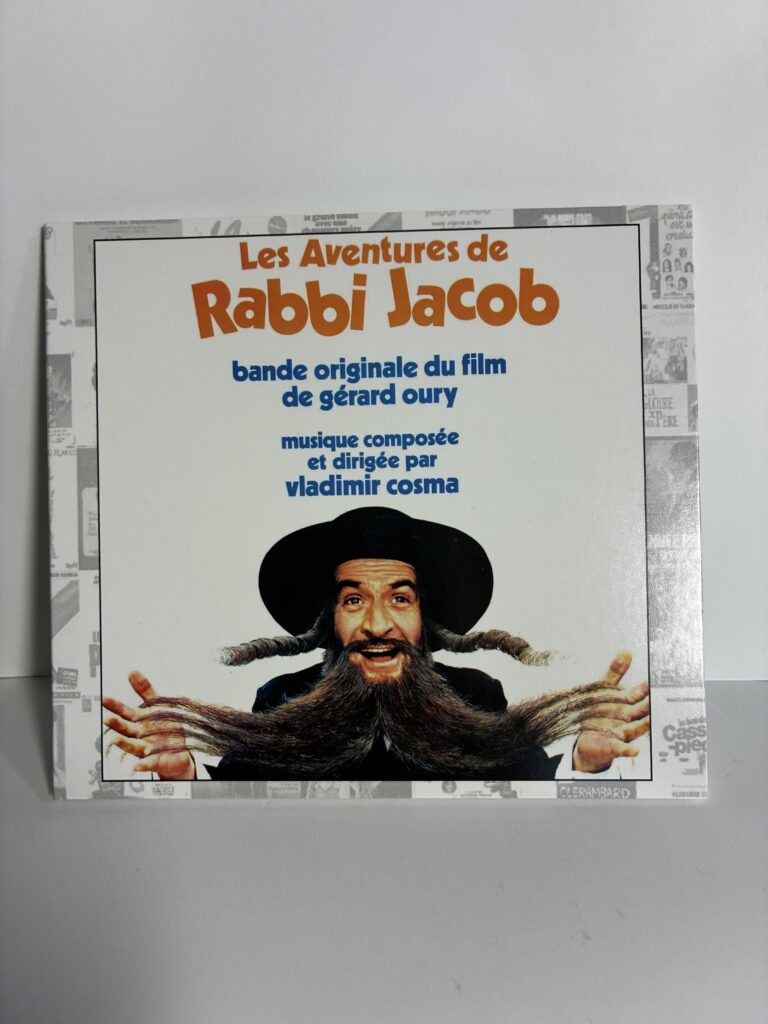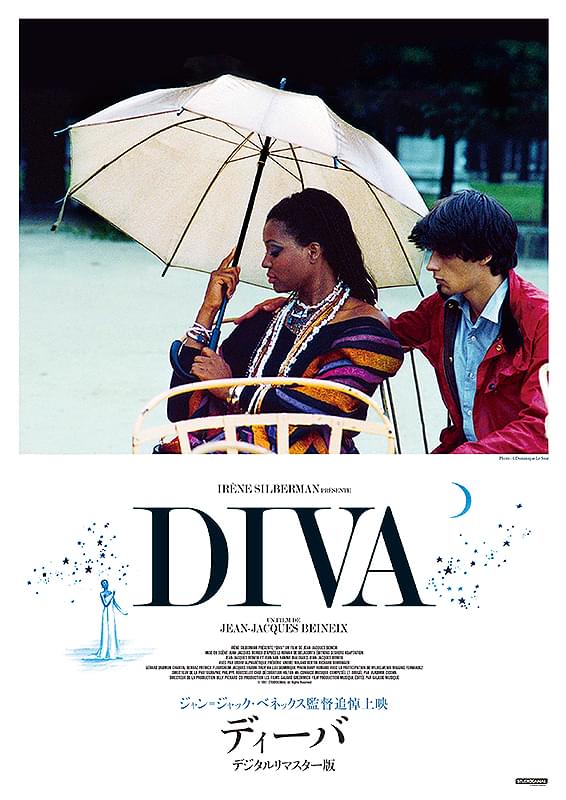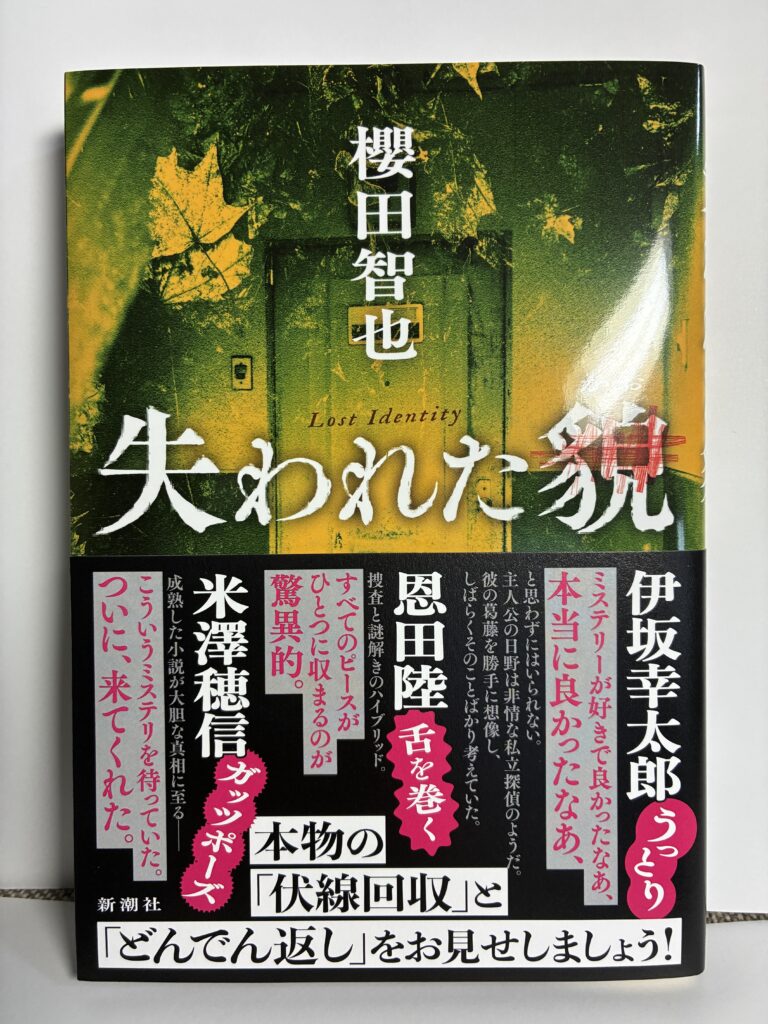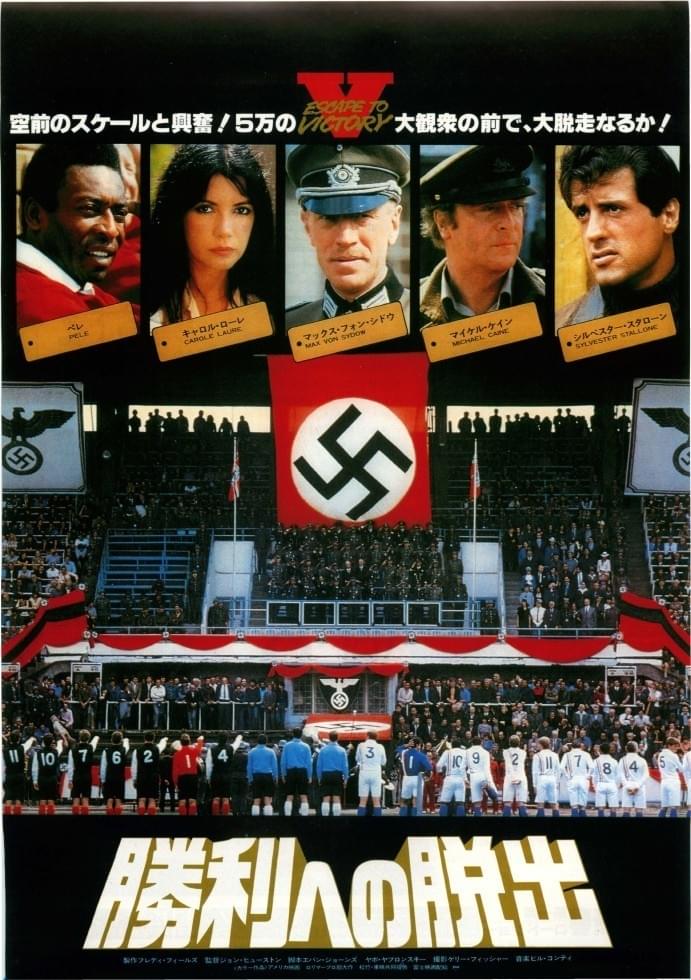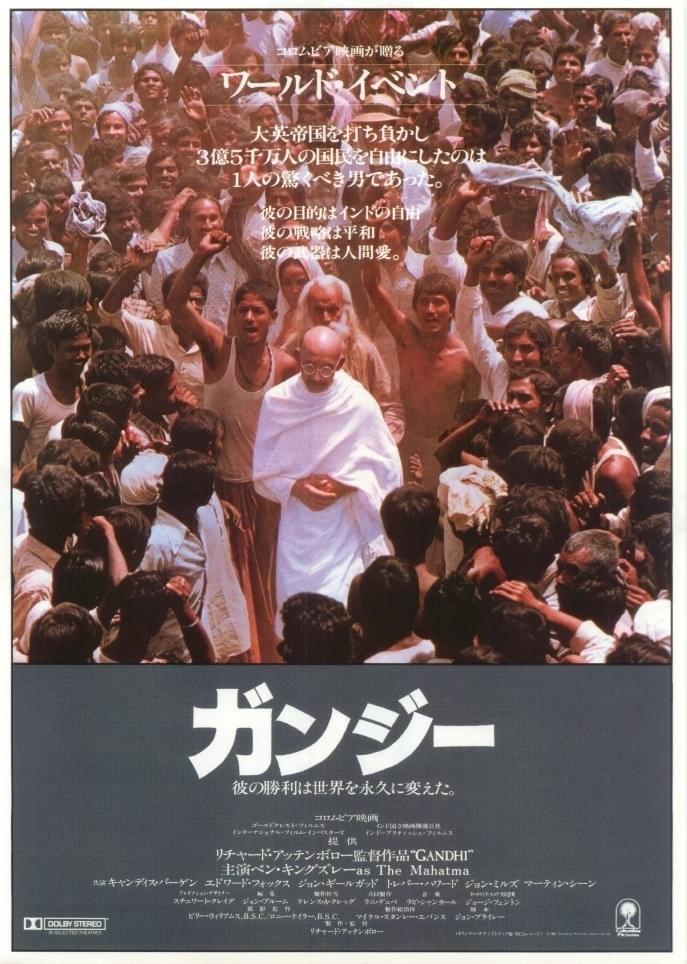『イミテーション・ゲーム』とか『黄金のアデーレ』とか、あと『アポロ13』など実話ベースの映画が大好きで、時々意味もなく観たくなるのですが、今回、Blu-rayを購入していたのになぜかこれまで一度も観ていなかった『ドリーム』(2016年)を観てみました。
もちろん2017年の日本公開時には劇場で鑑賞し、とても感動したからBlu-rayを買ったのですが、細かいところは忘れているところもかなりあったので、新鮮に鑑賞することができました。
米ソが宇宙開発競争を繰り広げていた1961年。NASAで働く黒人女性グループのキャサリン、ドロシー、メアリーはそれぞれ実力も向上心もありながら人種差別的な職場環境に苦しんでいた。ある日、宇宙特別研究本部の計算係に抜擢された数学者のキャサリンは、その実力で上司のハリソンに認められ、マーキューリー計画の重要な計算を任されるようになるのだが…。
人種差別、女性差別が当たり前だった時代に、自らの意志と努力によって運命を切り拓いた人たちの物語なので、観ていて爽快だし、話の筋や結末を知っていても、その展開を息を呑んで見つめてしまう、実に素晴らしい作品だと再認識。
まず、主人公3人の俳優、タラジ・P・ヘンソン、オクタヴィア・スペンサー、ジャネール・モネイが何といっても素晴らしい。この3人それぞれの個性が立っていて、尚且つ3人の芝居のアンサンブルが実に見事。車が故障して3人が掛け合いをするファースト・シーンから、すぐに物語の波に乗ることができる。脚本や演出もツボを心得ていて、登場人物や物語の進行に混乱が生じないように要素のバランスがうまく配慮されているのも素晴らしい。
そしてこの3人と共に、作品のキーパーソンとなるのが上司ハリソン役のケビン・コスナー。常に冷静だが、プロジェクトの達成に集中するあまりに周りが見えなくなるタイプの男を、肩の力を抜いた感じで演じていてすごくいい。彼がキャサリンにオフィスから近いトイレを使ってもらえるように白人専用の看板を破壊するという印象的なシーンがあるのだが、その時の彼のセリフが吹き替え版では「NASAでは全員が同じ色だ」となっている。一方字幕版では「NASAでは小便の色は同じだ」となっていて、言わんとするところは同じだがニュアンスがちょっと違っているのだ。吹き替え版はキレイな表現だけど、字幕版の方がずっと彼の心情に寄り添った“本音”感があって好きでした。

あと今回再鑑賞して驚いたのが、何とグレン・パウエルが出演していた!と言うことです。この映画の日本公開当時(2017年)はまだ『トップガン/マーベリック』(2022年)は公開されていなかったので、我々は彼を全く認識できていなかったのだが、マーキュリー計画のパイロットという重要な役で、出番も結構あってメインキャストとしっかり絡んでいるし、今見るととても印象的な演技をしていた。そして当時からコクピットが似合う役者だったということを発見できた。
さらに、これはすっかり忘れていたことだが、キルステン・ダンストとマハーシャラ・アリも出ていました。キルステンは主人公たちの上司となるNASAの白人女性を嫌味たっぷりに演じていてお見事。マハーシャラはキャサリンと出会い、恋をする軍人役で彼もまた『グリーンブック』(2018年)より前の出演になるので、当時はまだそんなに知られてはいなかっただろう。そう考えるとこの映画は今やかなりの豪華キャストによる作品になっていますね。
『ドリーム』(2016年製作 2017年日本公開 監督:セオドア・メルフィ) Blu-ray鑑賞 20世紀フォックス ホーム エンターテイメント ジャパン